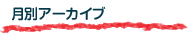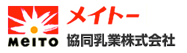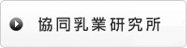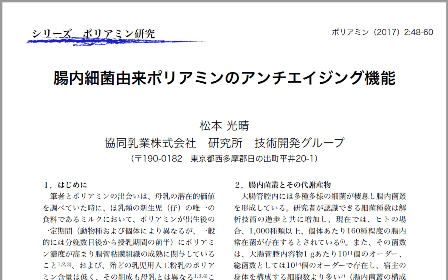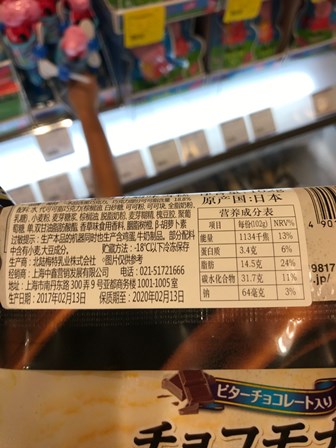12/26
よいお年を!

実は、今から出張でして、
明日、明後日と出張。
従いまして、本年は、これをもって、最後のブログとさせて頂きます。
なんで、こんな年末に色々あるのでしょうか?
しかも、色々と準備がしんどい仕事が連発です。
只今の準備完成度10%(12/26 12:00現在)
まあまあ追い詰められている感あり。
新幹線内が勝負です。
頑張ります!
例年、年末ブログは1年のブログを振り返っておりましたが、
今年はその時間が全くありませんわ。
年間ウンコ回数もどんなペースでカウントされているのか、
全くわかりません。
年明けの楽しみとしておきます。
では、みなさま、良いお年を!